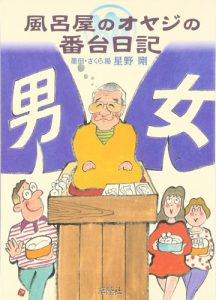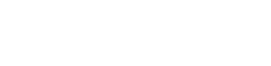平成5(1993)年に創刊した銭湯PR誌『1010』のバックナンバーから当時の人気記事を紹介します。
昭和30年代初期。私は銭湯の番頭と屋台オーナーの二足のわらじ生活を楽しんでいた。番頭としての仕事を終え、「夜回り」と称して仲間と屋台を飲み歩く。私が顔を出すと、「ご苦労さんデス」とヤカンの中から1合入りの燗(かん)差しを抜いて、お茶代わりに出してくれる。近況をひとしきり聞いたら、次の屋台へ……。5台すべてを回る頃には普通ではなくなっている。
そんなある晩のことだった。「トーシロがこんな所で遊んでんじゃねえ!」。突後から突っ掛かってきた。屋台のカウンターにしこたま胸を打ち付け、プロパンが爆発したのかと振り向いた途端、一発食らった。おでんやコップが飛び散り、私は長いすにもたれかかるように倒れた。低い姿勢が幸いして相手の足元がよく見える。とっさに足払いが出た。一瞬、赤ちょうちんの光で目がくらんだ。気付けば相手の姿がない。路地の向こうで酔客たちが騒いでいる。見ると先ほどの相手が側溝に落ちていた……。
こんなやり取りが何回か続いた。私がショバ代タダで借り受けた物件、それは対立する組織の縄張りの境界線上に立地していたのだ。そんなことを知る由もない私だったが、「5台の売り子の生活を守る責任がある」と、危険と隣り合わせの毎日を送っていた。
銭湯のほうはと言えば、毎日9時に起床。同時にダイハツの三輪車に乗って燃料取りへ出発。1日分の燃し物を加工して、湯をつくり、開店と同時に「流し」に出る。白いサラシを腹に巻き、半股引(はんだこ)をはけば、いなせな番頭姿の出来上がりだ。扱い方がよく、好感度が高ければ、チップを弾んでくれる粋なお客さんもかなりいた。
しかし、よいことばかりではない。冬場、流し場と釜場を駆けずり回っていると、湯水と冷気で指の先、足の裏が割れ、血が流れる。足の指は全部水虫で、その赤肌にせっけん水が染みる。指先が割れようが、血が流れようが、背中のツボを押すときは力を込める。「それが商売、仕事というヤツだ! 悔しいと思ったら、これをバネに早く独立しろ!」
オヤジさんは言う。まったく的を射た「愛のムチ」である。こんなことでキレるようでは、奉公人は勤まらない。
二足のわらじも4~5年が過ぎたころ、私はアパートを所有するまでになっていた。相変わらず小競り合いは続く。組織に関係のない私は、「弾よけ」の盾になっていたのだ。老練な親分にすれば、どこまで踏ん張れるか、お手並み拝見だったのだろう。私も懸命に応戦していたが、親からもらった体に少々傷が入りもした。御殿場に自らの墓を買ったのも、そのころだ。
昭和39年の東京オリンピックが近づくと、街の美化運動として不動式の屋台は撤去されることになった。警察の強制指導が入ったのを機会に、私は屋台稼業に別れを告げたのだった。
【著者プロフィール】
笠原五夫(かさはら いつお) 昭和12(1937)年、新潟県生まれ。昭和27(1952)年、大田区「藤見湯」にて住み込みで働き始める。昭和41(1966)年、中野区「宝湯」(預かり浴場)の経営を経て、昭和48(1973)年新宿区上落合の「松の湯」を買い取り、オーナーとなる。平成11(1999)年、厚生大臣表彰受賞。平成28(2016)年逝去。著書に『東京銭湯三國志』『絵でみるニッポン銭湯文化』がある。なお、平成28年以降は長男が「松の湯」を引き継ぎ、現在も営業中である。
【DATA】松の湯(新宿区|落合駅)
銭湯マップはこちら
今回の記事は1999年6月発行/38号に掲載
■銭湯経営者の著作はこちら
「東京銭湯 三國志」笠原五夫
「絵でみるニッポン銭湯文化」笠原五夫
「風呂屋のオヤジの番台日記」星野 剛
「湯屋番五十年 銭湯その世界」星野 剛(絶版)