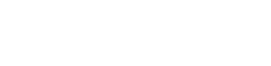東武東上線大山駅を降りると目と鼻の先に、ハッピーロード大山商店街の長いアーケードが続く。駅を出た人々の多くが吸い込まれていくその先には、魅力的な商店が並び、活気にあふれている。そんな商店街に後ろ髪を引かれつつ、駅から南に10分ほど歩くと、住宅地の一角にみやこ湯が現れる。
創業が1956(昭和31)年4月と、約70年の歴史を誇るみやこ湯。創業20年目の1976(昭和51)年に現在のビル型に改築し、すでに50年近くの月日が流れる。移りゆく池袋近辺の町並みの中で、変わらぬ姿で町を見守り続けるみやこ湯には、情緒と貫禄が感じられる。
左右に分かれた入り口を通り、下駄箱、番台を抜けのれんをくぐると広々とした脱衣場があり、その向こうに鮮やかに描かれた富士山、北海道大沼公園と駒ヶ岳のペンキ絵が目に入ってくる。脱衣場・浴室共にレトロさを感じさせつつも、丁寧な手入れと清掃が行き届いた店内からは、来る人みんなに気持ちよく利用してもらいたいという経営者の心意気もうかがえる。
浴室に目を移すと、手前の洗い場は余裕をもってカランを配置。備え付けのシャンプー・ボディソープがあり、番台でタオルのレンタルも受け付けているため、ふらっと立ち寄れるのもうれしいところだ。
湯船にはジェットバス、バイブラバスを備え、5、6名は入れる大きめのサウナと、銭湯には珍しい余裕ある深さと広さを兼ね備えた水風呂も鎮座している。サウナ後のクールダウンにベストな、水風呂が近接した配置はサウナ好きから好評だという。
さぞやいろいろなサウナ好きが訪れていることだろうと壁を見ると、ネプチューンの原田泰造さんのサイン色紙が目に留まる。それもそのはず、サウナブームを巻き起こしたテレビドラマ『サ道』(テレビ東京系)の記念すべき第一話に、原田さん演じる主人公がサウナにはまったきっかけの店としてみやこ湯が登場するのだ。その影響もあって、みやこ湯は一部のサウナ好きから“サウナの聖地”と呼ばれている。
今回、ドラマ『サ道』の撮影場所に選ばれた経緯など、みやこ湯二代目店主・斉藤五十三(いそみ)さん、妻の美知子さん、長男の賢弘(よしひろ)さん、次男の高史(たかふみ)さんにお話をうかがう機会をいただいた。
――来年で70周年を迎えるとのことで、おめでとうございます! みやこ湯の歴史がどのように始まったのか教えていただけますか。
五十三:もともとは義父の兄が新潟から出てきて、北区赤羽で銭湯を営んでいたことが始まりです。当時すでに2軒を経営していて、3軒目となる銭湯の営業を開始するタイミングで義父に声がかかり、経営を任される形で始まったのが、このみやこ湯です。
――約70年も歴史をお持ちだと、常連さんの層も厚そうですね。
五十三:そうですね。大変多くの常連さんたちに支えられています。最近はサウナブームの影響もあり、遠くの区からわざわざお越しになる方もいて、常連さん以外のお客さんも増えているなと肌で感じます。
――ドラマ『サ道』の第一話、拝見しました!
美知子:ありがとうございます。『サ道』の存在はかなり大きくて、放送されてからもう5年以上経ちますが、いまだに「ドラマを見てずっと来たかったんです!」とお声がけくださる方もいますね。
もともとの常連さんはもちろん変わらず来てくださってますが、ドラマの影響か、ここ最近は女性のお客様も本当に増えて、貸出用のタオルの在庫を切らさないようにひたすら洗濯を繰り返しています!(笑)
――ドラマの撮影場所に選ばれたのはどういった経緯なのでしょうか。
五十三:若い方たちにとって、銭湯がどうしても縁遠い場所になりつつある中、メディアで取り上げてもらうことで銭湯業界自体が盛り上がったら良いなと思い、取材や撮影などのご要望をいただいた場合は、基本的に受けるようにしています。
そうやっていくつか取材や撮影などに応じていた流れで『サ道』の収録依頼も来たと記憶しています。『サ道』以外にも、毒蝮三太夫さんがラジオ番組の公開生放送に、品川庄司の品川ヒロシさんやロバートの秋山竜次さんが映画『戦湯〜SENTO〜』の撮影にいらっしゃいましたよ。
――みやこ湯さんは撮影場所としていろいろ貢献されているのですね。
五十三:ありがたい話です。メディアとはちょっと違いますが、特に印象に残っているのが、フランス人の女性カメラマンさんが飛び込みでいらっしゃって、日本のTATOOの写真集の撮影場所にみやこ湯を使いたいと相談を受けた件ですね。
撮影当日、どんな感じになるのかと思っていたら、ご自分で交渉したのか、入れ墨の入った方々を10人近く集めて、精力的に写真を撮られていました。なかなか立ち会うことのできないシーンだったので、とても記憶に残っています。
――それは壮観だったでしょうね!
高史:少し話は変わるんですが、海外の方にとってのお風呂といえば、今、私はタイのバンコクに家族で住んでいます(編注:取材時は一時帰国中)。バンコク市内には「湯の森温泉」という有名なスパがあり、日本式の入浴文化がタイで味わえる唯一の施設になってます。そこに今年の正月、家族で行ったんですが、日本人に限らず海外の方々でごった返していました!
大衆浴場という文化は世界でも珍しいと思っていたのですが、日本の外でもしっかりと根付き始めていて、今後日本の銭湯が海外からのお客さんでもっとにぎわう可能性もあるなと感じましたね。
――確かに現在インバウンドのお客様が銭湯を訪れるケースも増えていると聞きます。海外の方々にアプローチするうえでも情報発信が欠かせない時代ですが、みやこ湯さんはSNSにも力をいれていますね。
賢弘:はい、私が担当してX(@MIYAKOYU1956)やInstagram(miyakoyu1956)を日々更新しています。
SNSはビジュアル重視の側面があるんですが、銭湯で“映える”要素が多いのになかなか知られる機会がないのがもどかしいな、と。ボイラー室とかお店の裏、お客さんが普段行けない場所とか、強いアピールになりますよね。
だから、自分たちで情報を積極的に発信していく必要があると思い、日々投稿するネタを考えながら更新しています。
――みやこ湯さんは定期的に変わり湯もされているので、そういった情報がSNSにあがっていると、「行ってみよう!」となるかもしれません。
賢弘:そうですね、SNS上にお店の情報を投稿という形で積み重ねていくことで、銭湯としてのユニークさがお客さんにもっとわかりやすくなると思っています。
ただ、SNSはともすれば一方的な告知に終始してしまいがちなので、できるだけお客さんとのコミュニケーションツールになるよう、コメントしやすいような動画を投稿することなどを心がけています。時にはお客さんからコメントやご質問をいただき、それに対してコメントを返していくことによって、私たちがどのような思いでみやこ湯を続けているのかが、少しでも伝わるんじゃないかと期待しています。
――伝わると思います! いろいろなお話をありがとうございました。最後に今後のみやこ湯についてコメントをいただけますでしょうか。
美知子:昨今のサウナブームで銭湯業界も少しずつにぎわいを取り戻してきましたが、それでも若い方にとってはまだまだなじみがない場所だと思います。ですが、先代の父は「みやこ湯をずっと続けていきたい」と語っていましたし、私たちも100年を目指して営業を続けていきたいですね。
五十三:サウナブームは一つのチャンスであることは間違いないと思います。ただ、サウナ熱が一般にも高まった一方で、銭湯自体の持つ魅力というのは必ずしもお客さんに伝わっていないんじゃないかという不安もあります。
だから、若い方たちにたくさん来ていただけるのはとてもうれしいです。ただ、中高年層や家族連れのお客さんにも目を向けて、幅広い方々に長く愛される施設を目指していきたいとも思っています。やはり銭湯は憩いの場であってほしいので、地元の方にとっても“居心地の良い施設”であり続けられるよう努力していきます!
――貴重なお話、ありがとうございました!
(写真・文:銭湯ライター 中山英樹)
【DATA】
みやこ湯(板橋区|大山駅)
●銭湯お遍路番号:板橋 13
●住所:板橋区熊野町34-14(銭湯マップはこちら)
●TEL:03-3956-0631
●営業時間:15時半~24時
●定休日:金曜、第3木曜
●交通:東武東上線「大山」駅下車、徒歩10分
●ホームページ:https://1010itabashi.or.jp/facility/みやこ湯/
●X(旧Twitter):@MIYAKOYU1956
●Instagram:miyakoyu1956
※記事の内容は掲載時の情報です。最新の情報とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。